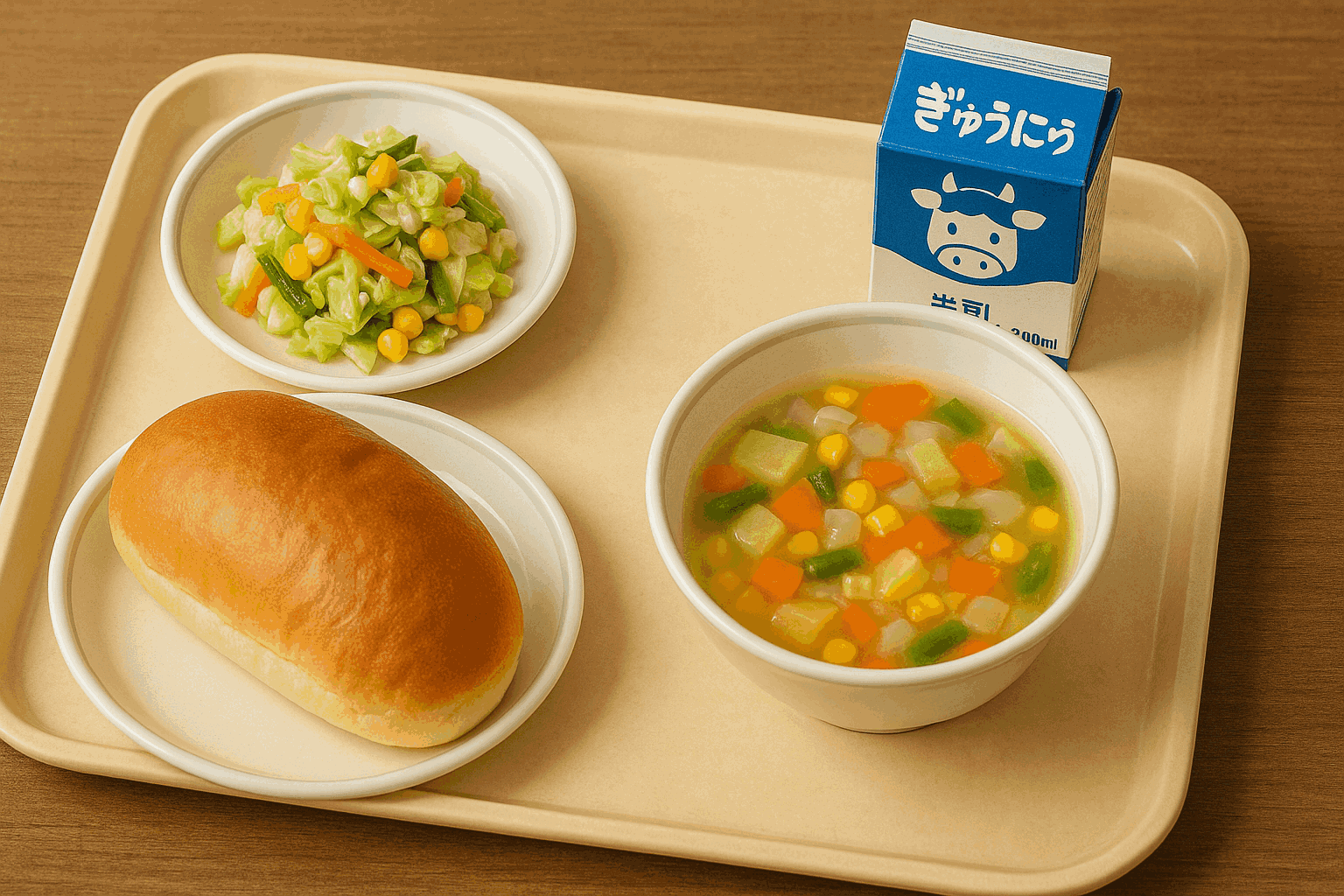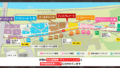SNSで話題の「給食の挨拶廃止」
2025年4月末、X(旧Twitter)を中心に「学校給食で『いただきます』と『ごちそうさま』を廃止する動きがある」という噂が急速に拡散しました。
中には「PTAが“給食費を払ってるのに感謝を強要するな”とクレームを入れ、学校が挨拶をやめた」といった具体的な投稿も出回りました。
果たしてこれは事実なのでしょうか?文部科学省の方針や、教育現場での実例、SNSでの情報をもとに、真偽を検証していきます。
SNSで広がった「挨拶廃止」の噂とは?
噂の出所は、2025年4月に投稿されたXのあるポスト。
投稿者は「子どもが通う学校で、PTAからの要望により『いただきます』を言わなくなった」と主張し、瞬く間に拡散されました。
その後、Threadsや知恵袋など他のSNSにも同様のエピソードが転載され、
- 「○○県の学校でも同じことが起きている」
- 「PTAがクレームを入れたら学校が言うのをやめた」
- 「宗教的な強制になるという理由で廃止された」
など、尾ひれがついた情報が増殖していきました。
しかし、これらの投稿には具体的な学校名や自治体名、日時、関係者の発言などが一切出てきません。信頼性に疑問のある情報が“あたかも全国的な動き”のように拡散されてしまったのです。
文科省の方針:「いただきます」は推奨されている
文部科学省が2019年に改訂した『食に関する指導の手引』には、明確に次のような記載があります。
「給食の時間は、食べ物や作ってくれた人への感謝の気持ちを表す教育の機会である」
つまり、食事に対する感謝の心を育むことは、今もなお教育上重要とされており、挨拶を推奨する立場は変わっていません。
「いただきます」や「ごちそうさま」といった言葉は、道徳や食育の文脈で大切に扱われているのです。
実際に「廃止」された学校はあるの?
一部の学校では「声をそろえて言うことを強制しない」という対応を取っているケースがあります。
例えば、2023年ごろには、千葉県内の小学校で、給食前の挨拶を“各自の判断で行う”という形にしたという実践報告もありました。
ただし、これは「宗教的な理由での配慮」や「給食嫌いの子への心理的負担軽減」が主な理由とされており、挨拶そのものを禁止したわけではありません。
「廃止論」が信じられやすい理由とは?
こうした噂がすぐに信じられてしまうのには、いくつかの背景があります。
- 「宗教の自由」や「強要」の話題はセンシティブで注目されやすい
- PTA vs 学校という構図が“それっぽく”聞こえる
- 実際に“挨拶の自由”を配慮した一部の学校事例があるため、誤解が広がりやすい
特に、SNSでは「事実かどうかより感情でシェアされる情報」がバズる傾向にあり、真偽の確認がなおざりになりがちです。
デマに踊らされないためのチェックポイント
噂や投稿を目にしたときには、次の点を確認しましょう。
| チェック項目 | 解説 |
|---|---|
| 出典があるか? | 学校名や公文書、日時などが明記されているか |
| 複数の報道があるか? | 信頼できる報道機関による裏取り報道があるか |
| 文科省の見解と一致するか? | 教育政策やガイドラインと矛盾しないか |
たとえば、今回の「給食での挨拶廃止」に関しては、NHK、朝日新聞、共同通信といった大手報道機関からの記事は確認されていません。
「いただきます」廃止は全国的な事実ではない
- 「学校給食で『いただきます』が廃止された」という噂に、公式な根拠はありません
- 文科省は今も食育の一環として挨拶を奨励しています
- 一部学校での配慮が誤解を呼び、SNSでデマが拡散した可能性が高い
SNSでは「正しい怒り」より「先走った怒り」が先に広まることも多くあります。
感情的になる前に、「その話、本当に?」と疑う力=情報リテラシーがいま、ますます必要とされているのです。